|
――ウェールズから響く音楽1:ポピュラー・ミュージック――  ■ダヴィズ・イワン(Dafydd Iwan) 歌/ウェールズ語 ■ダヴィズ・イワン(Dafydd Iwan) 歌/ウェールズ語 「何年間もの間、ウェールズ語を喋らない人々が、英語による注釈をレコードのスレーブ・ノートに書くように頼んできた。これは、シンガー・ソングライターとしての私のキャリーにおける、解決されないジレンマのひとつである。即ち、私たち――私独りではない――の仕事は、自身の権利としてウェールズ語で歌い、ウェールズ語で演じることを確立することだったのだ。」(ダヴィズ・イワン、2001年) 「何年間もの間、ウェールズ語を喋らない人々が、英語による注釈をレコードのスレーブ・ノートに書くように頼んできた。これは、シンガー・ソングライターとしての私のキャリーにおける、解決されないジレンマのひとつである。即ち、私たち――私独りではない――の仕事は、自身の権利としてウェールズ語で歌い、ウェールズ語で演じることを確立することだったのだ。」(ダヴィズ・イワン、2001年)2011年のアイステズヴォッドでは、2日に渡って出演したダヴィズ。私はその両日のステージを、幸運にも観る事ができた。最終日の公演を観ていたら、興奮した若い男がウェールズ語で何やら語りかけてきた。彼はこの異国の人間に向って、何度もこう語った――「なあ、最高のアーティストだろう?」。そう、ダヴィズ・イワンこそウェールズ・ポピュラー・ミュージックを代表する、最高のアーティストである。 ―― ―― ―― 「聖デヴィッドの日はいつ?」と問われれば、イワンは、「毎日」祝っていると答える(This Englans誌、2010年)。さらには自らの息子に、ウェールズの地名やケルト(Celt)という名前をつけるほど、愛国心がイワンは強い。その愛国心の高さは、イワンにウェールズ語存続とウェールズ解放のために、政治家として尽力させるほどだ。実際にウェールズ党の党首を2003年から2010年まで勤めている。 一方、イワンは歌手でもある。イワンは「ウェールズ語こそ我らの言語」と掲げ、一貫してウェールズ語で歌い、ウェールズ語によるフォーク・ソングを確立した。その意味でイワンは、現代ウェールズ・ポピュラー・ソングを語る上で、決して忘れることの出来ない存在だ。それほど政治とポピュラー・ミュージックの両方の世界に深く関わり、大きな影響を与えてきた。 たとえば一時期、ウェールズ語のフォーク・ソングといえば、ウェールズ語の存続とウェールズ独立を求めるプロテスト・ソングとしてみられた。極論すれば、かつて、ウェールズ語ポピュラー・ミュージック=ウェールズ愛国者らのプロテスト・ソングだった(現在ではそのようなことはない)。そしてこのウェールズ語フォーク・ソングを確立したのは、イワンその人だ(ゆえにイワンはウェールズ・フォーク・ソングの父と呼ばれる)。つまりこの図式を作り上げたのは、イワンその人だ。またイワンは、ウェールズのロック・シーンで最初に成功を収めた人物としても知られている。 ―― ―― ―― 1943年8月24日、南ウェールズのブリナマン(Brynaman)で、ウェールズ詩人の血を引く非国教徒系の牧師の家庭に生まれる。幼い頃から教会(chapel)でイワンは歌を歌い、母親から譜面の読み方を学ぶ。12歳の時に、北ウェールズのスラニューハスリン(Llanywchllyn)に移り住むが、建築を学ぶために南ウェールズのカーディフへと戻る。68年に卒業するが、彼は建築家への道は歩まなかった。彼の人生は、既に、歌手として、また、政治家としての道へと進み始めたいたのである。 遡って62年。この早い時期からイワンは、当時はニューウェーブと呼ばれた、ボブ・ディランらシンガー・ソング・ライターの影響を受け、ギターを片手に自作曲を歌っていた。66年にシングル“Wrth Feddwl Am Fy Nghymru”(わがウェールズについて考える時)で、デビュー。69年には、ヒュー・ジョーンズ(Huw Jones)とともにウェールズの最重要レーベルとなるサイン(sain)を設立。ここから、処女アルバムCarloがリリースされる。 また同じ頃から、ウェールズ語協会(the Welsh Language Society)の創立にかかわる。程なくしてイワンは、この運動の中心的役割を果たすようになった。“非暴力的”な活動を謳う協会だったが、その運動はしかしながら、実力行使も辞さなかった。たとえば当時、ウェールズ国内での交通標識は全て英語であった。これに反対した同協会は、ウェールズ語の交通標識、もしくは英語とウェールズ語のバイリンガルによる交通標識を強く求めた。そしてそれは、英語の交通標識をウェールズ語に強制的に書き換えるなどエスカレートしていった。このような実力行使の結果、70年にはイワンは投獄され、それに反対するメンバーによってデモ行進が行われもした。  英語とウェールズ語のバイリンガルな交通標識を求めたレコード のために撮影されながら、お蔵入りとなった有名な写真(1970年)。 70年代末からは、鉄の女と言われたマーガレット・サッチャー首相(当時)を、その活動の中で公然と批難し、フォークランド戦争開戦直前に反戦歌を歌っている。だがそのダヴィズも、サッチャーが強行した84-85年の炭鉱閉鎖には口をつぐんでいる。これは彼らが理想とするウェールズにとって、炭鉱を中心に栄えた英語文化圏が解体すべきものだったことを暗にほのめかしている。 なお82年からはウェールズ伝承歌バンドの中でも最有力バンド、アル・ログと初共演を果たし、83年よりツアーに出ている。この共演からは、シングル“Cerddwn Ymlaen / Y Gelynnen”と2枚のアルバムRhwng Hwyl A ThaithとYma O Hydを残している。なおシングル曲のA面(Cerddwn Ymlaen)のみ、Rhwng Hwyl A Thaithに収録されている。  シングル“Cerddwn Ymlaen / Y Gelynnen”レコーディング時。 右から2番目がダヴィズ・イワン。
右はステージの前を埋め尽くす観客たち。 (撮影:Yoshifum! Nagata) [アルバム(選)] ■Bod Yn Rhydd / Gwinllan a Roddwyd (90) (Sain / SCD 8085)  79年のBod Yn Rhyddと86年のGwinllan a Roddwydを1枚のCDにカップリング。この間にアル・ログとの2枚の共演盤Rhwng Hwyl A ThaithとYma O Hyd(Dafydd Iwan ac Ar Log / Tma O Hyd参照)が挟まることになる。やはり政治色が強いが、その中で「ウェールズ語が英語と同じくらい“必要不可欠”にならねば、ウェールズ語は生き延びることができない」と歌う“Mae'r Saesneg Yn Essensial”(英語は必要不可欠)、賛美歌“Gweddi Dros Gymru”、神の声を歌った“Mi Glywaf Y Llais”や船乗りの歌(伝承歌)“Santiana”などヴァラエティにもやや富んだアルバムになっている。この“Santiana”ではアカペラを披露、いつものダヴィズ節よりも深いウェールズの闇を聴かせる。 79年のBod Yn Rhyddと86年のGwinllan a Roddwydを1枚のCDにカップリング。この間にアル・ログとの2枚の共演盤Rhwng Hwyl A ThaithとYma O Hyd(Dafydd Iwan ac Ar Log / Tma O Hyd参照)が挟まることになる。やはり政治色が強いが、その中で「ウェールズ語が英語と同じくらい“必要不可欠”にならねば、ウェールズ語は生き延びることができない」と歌う“Mae'r Saesneg Yn Essensial”(英語は必要不可欠)、賛美歌“Gweddi Dros Gymru”、神の声を歌った“Mi Glywaf Y Llais”や船乗りの歌(伝承歌)“Santiana”などヴァラエティにもやや富んだアルバムになっている。この“Santiana”ではアカペラを披露、いつものダヴィズ節よりも深いウェールズの闇を聴かせる。■Dafydd Iwan ac Ar Log / Tma O Hyd (93) (Sain / SCD 2063)  ウェールズ・フォーク・ミュージックのドン、ダヴィズ・イワンとアル・ログがタッグを組み、82年と83年にかけてツアーに出た。その結果、2枚のアナログ盤Rhwng Hwyl A Thaith(1-10曲目)とYma O Hydが生まれ、その両方を収録したのが本CDである。両者の持ち味である、ダヴィズ作詞作曲のプロテスト・ソングと、アル・ログ編曲による伝承歌が混在し、その結果、1960-80年代のウェールズと18世紀ごろのウェールズの両方の姿が浮かびあがってくる。その大部分でダヴィズが歌っているが、演奏がアル・ログ主体になっているので、言葉さえわからなければ、政治臭さは感じない。その確かな演奏のおかげで、むしろ、ダヴィズが自身のバンドを従えている時よりも、ダヴィズの声の良さが前に出ているように感じる。タイトル曲にも選ばれた「まだここで」(“Tima O Hyd”)は、ダヴィズがアル・ログとの83年のツアー中に書いた最も有名なアンセムだ。ウェールズ的な暗さと、力強さ、そして、フォーク・ソングの要素が絶妙のバランスで絡み合っている傑作である。 ウェールズ・フォーク・ミュージックのドン、ダヴィズ・イワンとアル・ログがタッグを組み、82年と83年にかけてツアーに出た。その結果、2枚のアナログ盤Rhwng Hwyl A Thaith(1-10曲目)とYma O Hydが生まれ、その両方を収録したのが本CDである。両者の持ち味である、ダヴィズ作詞作曲のプロテスト・ソングと、アル・ログ編曲による伝承歌が混在し、その結果、1960-80年代のウェールズと18世紀ごろのウェールズの両方の姿が浮かびあがってくる。その大部分でダヴィズが歌っているが、演奏がアル・ログ主体になっているので、言葉さえわからなければ、政治臭さは感じない。その確かな演奏のおかげで、むしろ、ダヴィズが自身のバンドを従えている時よりも、ダヴィズの声の良さが前に出ているように感じる。タイトル曲にも選ばれた「まだここで」(“Tima O Hyd”)は、ダヴィズがアル・ログとの83年のツアー中に書いた最も有名なアンセムだ。ウェールズ的な暗さと、力強さ、そして、フォーク・ソングの要素が絶妙のバランスで絡み合っている傑作である。■Cynnar (98) (Sain / SCD 2180) 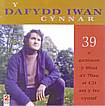 全39曲。2枚組みCDの本作は、イワンの60〜70年代にリリースされた曲を中心的に編集されている。この時期の作品は既に入手困難のものが多く、それだけに、本作は彼の初期の声を伝える重要な作品となっている。デビュー・シングル(ただしここに収録されたのは、72年のLP収録のもの)を筆頭に、66〜73年にリリースしたEPから18曲、81年のライヴ音源の収録が嬉しい。ディスク2の15曲目の終わり近くでは、聴衆と一緒に曲を合唱する様子から、ウェールズ人の合唱好きが伺える。どれも地声を生かした歌でありながら、そこには幼い頃から教会で歌っていたという年季と力量を感じさせる。ディスク1の6曲目のアカペラには、思わず聴き入ってしまうほどだ。しかしながら、音楽的にはフォーク、ロック、ハワイアンなどの様々なスタイルを取り入れてはいるものの、十分に咀嚼し、消化できているとは言えない。やはりこの人にとってはウェールズ語で歌うことが一番の目的であり、それが良いか悪いかは別として、音楽的なことは二の次なのだと感じずにはいられない。 全39曲。2枚組みCDの本作は、イワンの60〜70年代にリリースされた曲を中心的に編集されている。この時期の作品は既に入手困難のものが多く、それだけに、本作は彼の初期の声を伝える重要な作品となっている。デビュー・シングル(ただしここに収録されたのは、72年のLP収録のもの)を筆頭に、66〜73年にリリースしたEPから18曲、81年のライヴ音源の収録が嬉しい。ディスク2の15曲目の終わり近くでは、聴衆と一緒に曲を合唱する様子から、ウェールズ人の合唱好きが伺える。どれも地声を生かした歌でありながら、そこには幼い頃から教会で歌っていたという年季と力量を感じさせる。ディスク1の6曲目のアカペラには、思わず聴き入ってしまうほどだ。しかしながら、音楽的にはフォーク、ロック、ハワイアンなどの様々なスタイルを取り入れてはいるものの、十分に咀嚼し、消化できているとは言えない。やはりこの人にとってはウェールズ語で歌うことが一番の目的であり、それが良いか悪いかは別として、音楽的なことは二の次なのだと感じずにはいられない。■Dafydd Iwan A'r Band / Cyfrol 1 (2001) (Sain / SCD 2239)  2000年に行われたライヴ演奏を収録した全2作のライヴ盤の第1弾が、本作である。50半ばを過ぎたというのに、力強い声に衰えはない。またそのウェールズ独立を声高に叫ぶ姿も、健在である。サッチャー政権の幕開けの時に、ウェールズに自由をと願う“Bod yn rhydd”(「自由になるために」)で、このアルバムは幕をあける。以後、イワンはその政治色を隠そうとしない。むしろ、激しく突きつけてくる。例えば、“Y wen phyla amser”(「あの時代の微笑みはかすむことはない」)では、ウェールズ党の創立者のひとり、D.J.ウィリアムスを歌い、“Wrth feddwl am fy Nghymru”(「私のウェールズを考える時に」)では己の愛国主義者としての歴史を歌う。しかし最も強烈なのは、“Magi Thatcher”である。イワン曰く「鉄の女サッチャー称賛の賛歌」とのことだが、BBCから放送禁止となった事実を考えれば、その内容は想像できよう。その中で異色作が、レゲエのリズムに乗って歌われる“Can yr Aborijini”(「アボリジニの歌」)だ。表面上、この曲は白人に支配され、植民地化されたオーストラリアの原住民について歌ったものだ。だが、彼が自分たちウェールズ人の姿をここに重ね合わせているのは、疑いの余地がない。そしてこの曲は、翳りあるメロディーをこれでもか、と、力強くうたう、ウェールズ人とウェールズへの賛歌“Yma o hyd”(「私たちは未だ残っている」)に引き継がれ、アルバムは終る。 2000年に行われたライヴ演奏を収録した全2作のライヴ盤の第1弾が、本作である。50半ばを過ぎたというのに、力強い声に衰えはない。またそのウェールズ独立を声高に叫ぶ姿も、健在である。サッチャー政権の幕開けの時に、ウェールズに自由をと願う“Bod yn rhydd”(「自由になるために」)で、このアルバムは幕をあける。以後、イワンはその政治色を隠そうとしない。むしろ、激しく突きつけてくる。例えば、“Y wen phyla amser”(「あの時代の微笑みはかすむことはない」)では、ウェールズ党の創立者のひとり、D.J.ウィリアムスを歌い、“Wrth feddwl am fy Nghymru”(「私のウェールズを考える時に」)では己の愛国主義者としての歴史を歌う。しかし最も強烈なのは、“Magi Thatcher”である。イワン曰く「鉄の女サッチャー称賛の賛歌」とのことだが、BBCから放送禁止となった事実を考えれば、その内容は想像できよう。その中で異色作が、レゲエのリズムに乗って歌われる“Can yr Aborijini”(「アボリジニの歌」)だ。表面上、この曲は白人に支配され、植民地化されたオーストラリアの原住民について歌ったものだ。だが、彼が自分たちウェールズ人の姿をここに重ね合わせているのは、疑いの余地がない。そしてこの曲は、翳りあるメロディーをこれでもか、と、力強くうたう、ウェールズ人とウェールズへの賛歌“Yma o hyd”(「私たちは未だ残っている」)に引き継がれ、アルバムは終る。■Goreuon (2006) (Sain / SCD2400) 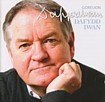 1965年から1990年の四半世紀の間に書かれた膨大なイワンの曲から、イワン本人が選んだ選曲集だ。「最後の王子」スウエリンを歌った“Cerddwn Ymlaen”(「歩き続けよう」)に始まり、ウェールズ語話者が英語教育で感じる矛盾と苦悩を歌った“Can yr ysgol”(「学校の歌」)や、自ら賛美歌とよぶ“Mi glwaf y llais”(「声を聞きて」)など編集盤とは思えない内容の濃さである。どれも甲乙つけがたいが、ウェールズ語運動の先駆者サンダース・ルイスの劇の台詞に基づいた“Gwinllan a roddwyd”(「葡萄園は与えられた」)は出色だ。ルイスの台詞に基づきながらも、イワンが歌った瞬間、それは全て独特のイワン節に染まる。この灰汁の強さこそが、イワンのシンガーとしての魅力である。デビュー曲“Wrth feddwl am fy Nghymru”(「私のウェールズを考える時に」)も、もちろん収録している。 1965年から1990年の四半世紀の間に書かれた膨大なイワンの曲から、イワン本人が選んだ選曲集だ。「最後の王子」スウエリンを歌った“Cerddwn Ymlaen”(「歩き続けよう」)に始まり、ウェールズ語話者が英語教育で感じる矛盾と苦悩を歌った“Can yr ysgol”(「学校の歌」)や、自ら賛美歌とよぶ“Mi glwaf y llais”(「声を聞きて」)など編集盤とは思えない内容の濃さである。どれも甲乙つけがたいが、ウェールズ語運動の先駆者サンダース・ルイスの劇の台詞に基づいた“Gwinllan a roddwyd”(「葡萄園は与えられた」)は出色だ。ルイスの台詞に基づきながらも、イワンが歌った瞬間、それは全て独特のイワン節に染まる。この灰汁の強さこそが、イワンのシンガーとしての魅力である。デビュー曲“Wrth feddwl am fy Nghymru”(「私のウェールズを考える時に」)も、もちろん収録している。■Dos i Ganu (2009) (Sain / SCD2600)  新作スタジオ録音。冒頭から、かなり良質のポップスが炸裂する。しかしそこを占めるのは、ダヴィズ節。そう、ここでは王道も王道のポップスが展開される一方で、全てはダヴィズ本人の灰汁(あく)の強い声とウェールズ語の歌詞が支配する。演奏はしっかりしているし、曲の構成も王道さながら。加えて、どの曲も人の心をつかむキャッチーさも持ち合わせている。しかしながら、ここでは音楽は二の次。ダヴィズの声とウェールズ語の歌詞さえあればよい。ダヴィズ自身の自負と、これまでのキャリアーに裏打ちされている強い説得力が、そう思わせる。だからダヴィズの声がスピーカーから流れた瞬間、心をわしづかみにされる。そしてダヴィズ・ワールドに否応なしに連れて行かれる。近年の彼の作品の中では、傑作中の傑作である。 新作スタジオ録音。冒頭から、かなり良質のポップスが炸裂する。しかしそこを占めるのは、ダヴィズ節。そう、ここでは王道も王道のポップスが展開される一方で、全てはダヴィズ本人の灰汁(あく)の強い声とウェールズ語の歌詞が支配する。演奏はしっかりしているし、曲の構成も王道さながら。加えて、どの曲も人の心をつかむキャッチーさも持ち合わせている。しかしながら、ここでは音楽は二の次。ダヴィズの声とウェールズ語の歌詞さえあればよい。ダヴィズ自身の自負と、これまでのキャリアーに裏打ちされている強い説得力が、そう思わせる。だからダヴィズの声がスピーカーから流れた瞬間、心をわしづかみにされる。そしてダヴィズ・ワールドに否応なしに連れて行かれる。近年の彼の作品の中では、傑作中の傑作である。[リンク] Dafydd Iwan ... 公式サイト。ウェールズ語と英語のバイリンガル。政治的な内容が濃い。 Plaid Cymru ... ウェールズ党の公式サイト。 Sain ... サイン・レーベルの公式サイト。オンライン・ショッピングあり。かなりお世話になっています。 このアーティストに関するウェブ・サイトの情報をお待ちしております。
ウェールズ?! カムリ!
文章:Yoshifum! Nagata (c)&(p) 2003-2013: Yoshifum! Nagata 「ウェールズを感じる――ウェールズから響く音楽――」へ。 サイト・トップはこちら。 |

